
先日小規模宅地に関する特例についてご紹介させていただきました。
その際、基本的に特例が使用できる人は「配偶者」と「亡くなった方と同居していた親族」
であるとご紹介しましたが、


特例として「家なき子制度」というものがあるので、重ねてご紹介させていただきたいと思います。
☆制度の概要
被相続人が所有していた自宅を、同居していなかった相続人が相続する場合でも、
小規模宅地等の特例を活用して土地評価額の80%(限度面積330㎡)を減額できるという制度です。
☆条件
①配偶者がいないこと
②同居相続人(相続放棄した人も含む)がいないこと
③居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち、
日本国籍を有しないものではないこと
④被相続人の親族であること
⑤申告期限(10ヵ月以内)までその宅地を所有し続けること(すぐに売買したりしないこと)
(※家なき子特例では、「申告期限まで所有し続けること」が要件とされていますが、その間の使用方法については制限がされていないため、
賃貸物件として貸付の用に供した場合でも適用対象となります。しかし申告期限までに売却した場合には上記の所有要件から外れてしまうため、家なき子特例の適用は不可となります。)
⑥相続開始前3年以内に、その取得者やその取得者の配偶者、その取得者の3親等内の親族またはその取得者と特別の関係にある法人が所有する家屋
(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと
⑦相続開始時に、その取得者が居住している家屋をその取得者が過去に所有したことがないこと
☆特例を受けるにあたっての必要書類
①被相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
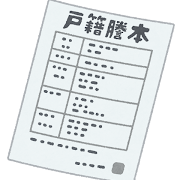
被相続人に配偶者や同居親族がいないことを証明する書類となり、
戸籍謄本は、相続開始日から10日以降に作成されたものが必要です。
②遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し

特例を申請する宅地を、申請者が相続しているかどうかを証明する書類が必要です。
③相続人全員の印鑑証明書

相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印したものが必要です。
④相続人の戸籍の附表の写し
過去の住所変更がわかる書類で、相続開始前3年以内の変更が分かるものが必要です。
⑤登記事項証明書や賃貸借契約書

相続開始前3年以内に居住していた家屋が
「自分の持ち家」・「配偶者の持ち家」・「3親等以内の親族の持ち家」
「特別の関係がある法人の持ち家」のいずれにも
該当しない家屋であることを証明する書類です。
そして相続開始時に居住していた家屋の登記事項証明書で、
「相続開始時において居住している家屋が、相続開始前のいずれの時も所有していたことがない」ことを証明する必要があります。
(住所変更を証明する資料としては、
土地を取得する人(相続人)の戸籍の附票を用意することが必要です。)
(基本的に、入居時に受け取っている賃貸借契約書を活用することができますが、
手元にない場合は不動産会社などへ問い合わせて用意してもらうようにしてください。)
※なお、親族でない人が所有する物件に暮らしていても、賃貸借契約を交わしていなかったり
賃料を支払っていなかったりすれば、「相続する人と特別の関係がある一定の法人」
などの理由でこの特例が使用できなくなるケースもありますので注意が必要です。
この記事を読んでいただき、「もしかしたらこの特例が使用できるかもしれないけど細かい制度の内容に関してはわからない」とのことでしたら
税理士をご紹介させていただきますのでお気軽にご相談ください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 丹羽




